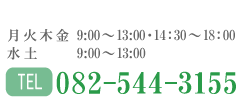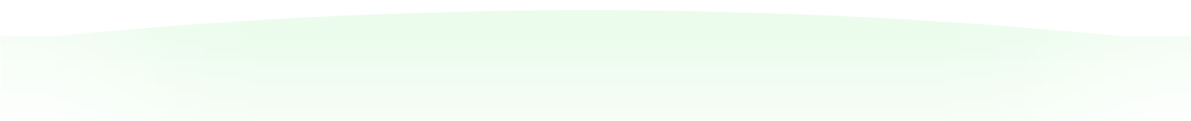令和3年12月29日
今日が今年最後の診療日、一年を振り返ってみるとやはりコロナに振り回された年だった。初めは武漢コロナがどのようなものかわからなかったので欧米と同様我が国も慎重に対処してきたが、一年も経つと日本ではインフルエンザと同等か、それ以下の脅威しかないことがわかってきた。にもかかわらず専門家と称する人たちは、欧米の状況をみて必要以上に制限を加え、マスコミはあおりに煽った。結果、飲食業をはじめ倒産する企業が増え、国力は大幅に低下してしまった。それに加えて無駄なバラマキ、財政はもうめちゃくちゃである。
このつけは若い人、子供たちにかかってしまう。早急にコロナを5類感染症にすべきなのに厚労省をはじめ専門家と称する人たちは、責任を取りたくないのでなにも言わない。
この一連の動きを見てわかったことは、政府・専門家集団・マスコミがなんと言おうとも、自分で考えて行動することがいかに大切かということである。当院の方針も同じで、今行われている検査・治療法が絶対的なものではなく、常にこの検査・治療は本当に患者さんのためになっているのかを真摯に考えながら行うということで、これは開業当初から変わらない。患者さんのためになることならなんでも取り入れるつもりである。検査結果も、わざわざ来院しなくても電話でいいと言うし、予約制にしないのも、今困っている人を見るのが医療だと思っているからである。今年も同じようにできたのはうれしいことだった。
今年もあとわずか、皆様よい年をお迎えください。
月別記事一覧 2021年12月
一年を振り返って
年賀状
令和3年12月22日
今年も年賀状を書く時期になった。例年、クリスマスまでには書き終えたいと思うのだが、生来の悪筆もありなかなか作業が進まない。最近、プリンターを変えたので宛先の印刷がうまくいくか心配だったが、案の定うまくいかない。散々試行錯誤した結果、印刷できるようにはなったが昨年の診療日誌を見ると、筆ぐるめに入れていた住所が消えていたという記述が。年に一回しか使わないので細かいことをほぼ忘れているのだろう。
毎年思うのだが、会うことはもうないと思われる元職場の先輩や同僚、もうやめてもいいのではと思う人などに対して、だらだらと出し続けるのはお互いによくないので止めようとする。でも相手からいただくと返信するとまた翌年は出さないと失礼に当たると思って出す。おそらく相手も同じようになっているのではないだろうか。来年は「これで最後にします」のメッセージを入れた賀状をつくろうかと思っている。
「カリ・モーラ」
令和3年12月16日
表題は「羊たちの沈黙」「ハンニバル」で一世を風靡した作家、トマス・ハリスの13年ぶりの作品である。訳者はもちろん高見浩氏である。ハンニバル・レクターという怪物を生み出した作者が今度はどんな作品を世に送り出すのか、世界中のファンが注目していたと思われる。自分もその一人であった。「ハンニバル」では主人公のハンニバルとクラリス・スターリングが最後には結ばれることで、心地よい読後感があった。
今度の作品は、コロンビアからアメリカに移住し、将来獣医になることを夢見て、いまは傷ついた野鳥などの保護に情熱を傾ける25歳のカリ・モーラが主人公で、子供好きの優しい心映えの女性だが、ひとたび悪党どもに挑まれると、一歩も引かずに手慣れたガンさばきで窮地を脱してゆく、という話である。アメリカの暗黒社会の描写が巧みで、思わず引き込まれてしまう。惜しむらくはヒロインにふさわしいヒーローがいればいいのにと思ったが、これがシリーズ化するなら登場するかもしれない。ただ、作者のトマス・ハリスは現在81歳、寡作であることを考えると新作は無理かもしれない。
近水園(おみずえん)
令和3年12月8日
週刊新潮のグラビアに「その後の織田家・豊臣家の知られざる名園」と称して岡山県の備中足守にある近水園(おみずえん)を紹介していたので行ってみた。
大坂夏の陣で淀君と秀頼は自害し、豊臣家は根絶やしになったと思えるが、秀吉の正妻、寧々の実家の木下家は徳川の世になっても豊臣姓を名乗ることを許されていた。寧々の兄、家定を藩祖とする木下家が支配していたのが備中足守2万5千石、その地に6代目藩主、木下きん定が18世紀に幕府の命を受けて京都御所の普請を行った際に、使われずに残った材木を持ち帰って造ったとされている。足守川の水を引いて池泉回遊式の園池を設け、池内に蓬莱島を兼ねた鶴島・亀島を浮かせ、御殿山(宮路山)を背景に、池のほとりには数寄屋造りの吟風閣が建ち、風情のある大名庭園である。グラビアの写真は紅葉がきれいなので期待して行ったけれど、残念ながらその季節は過ぎていた。近くに旧足守藩侍屋敷遺構もあり、歴史を感じさせられる一日になった。
師走
令和3年12月1日
今日から師走、月日の経つのはなんと早いことだろう。「光陰矢の如し」とはまさに言えて妙である。漢詩にはこのことに類した言葉が沢山あるようだが、洋の東西を問わずヒトの感覚は変わらないのだろう。
人生の残り時間が多いほど時間が経つのが遅く感じられ、残り時間が少なくなるほど早く感じられる、ということだと思う。自分の残り時間がどれくらいなのかを知りたければ、月日の経つ速さの感覚から推し量ればいいのではないだろうか。それが正しいなら、自分はあまり長くないことになる。
立川談志没後10年で発売された「作家と家元」に石原慎太郎氏との対談集、交流の様子が描かれているが、追悼文「さらば立川談志、心の友よ」に、死の直前に息遣いしかできなくなった談志に石原氏が電話の受話器を向けてくれるように家人に頼んで一方的にしゃべり、言葉はなくても二人だけで会話できたと思った、とあったが感動的である。こうして時代は過ぎてゆくのだろう。