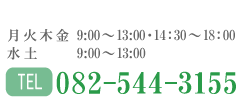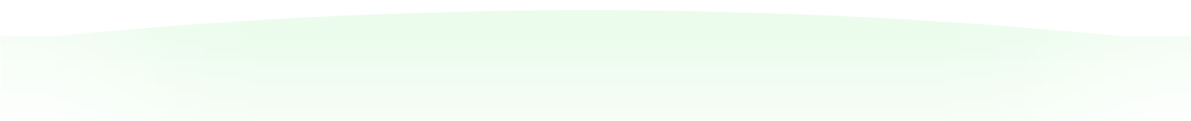令和元年8月30日
表題は外科医からホスピス医になり、現在はケアタウン小平クリニックを開設している山崎章郎氏の著書である。実はこの本は1990年に発売され、終末医療のあり方を考えさせる名著だったのだが、恥ずかしながら読んだことがなくて今回本屋で文庫本を手に取って初めて知ったわけである。
1970年代の初め頃に医師になった著者は、消化器外科医として研鑽を積んでいく過程で、癌のために病院で亡くなっていく人たちを見ていて思うことがたくさんあり、それが貯まってきて1990年に一般の人に考えてもらうためにこの本を書いたのである。当時は癌の告知はせず、最後までだまし通して病院で死ぬのが普通だった。それが患者にとってどんなに過酷で尊厳を傷つけることかを実話に基づいた物語によって著した。そういえば自分が医師になったばかりの頃、どの病院だったか末期の肺癌の患者さんが息をひきとろうとするときに、医師が昇圧剤を打って心マッサージをするのを見て「なんてひどいことをするのだろう、静かに逝かせてあげればいいのに」と思ったことがある。山崎氏は院内外の人々とターミナル研究会立ち上げ、末期ガン患者の延命・ガン告知・ホスピスの問題を提起、ホスピスに深くかかわり現在も続けている。
一方、現在もガン患者に対する過酷な治療は変わらず続いていて、手術・放射線・抗がん剤が通常である。これらはホスピスの考え方と真逆で、人は昔から病んで自然に亡くなっていくのがあたりまえであったのを、無理やり人工的に引き戻すようなものである。安らかに最後を迎えられるとは思えない。ガンと老化は治すことはできないと考えて、少しでも楽なように支えていくことが望まれる。
月別記事一覧 2019年8月
「病院で死ぬということ」
健康診断はいらない
令和元年8月23日
職場の婦人科健診で異常を指摘され受診する人が後を絶たない。調べてみても多くは検査する必要のない状態ばかりである。検診する側は、どんな些細なことでも指摘しておかないと後で訴えられたら困ると思うから様子を見ておいてもよいことでも指摘するのだろうし、受ける側は検診するよう職場から言われるので仕方なしに受けてその結果異常を指摘されて受診されるのだと思う。以前にも書いたが健康診断が役に立つという証拠はないにもかかわらず、厚労省の通達1本でいまだに検診が続けられているのが我が国の現状である。
職場検診が行われているのは世界中で日本だけだという。よその国が健診をしない理由は、健診が命を長引かせるかどうか調べた結果、意味がないことがわかったので各国は健診をやめたそうである。我が国も2005年に厚労省が研究班(班長:福井次矢・聖路加国際病院長)を作って健康診断の有効性を調べて報告書を出した。結果は、健康診断の大半の項目に有効性の証拠は薄い、ということであった。しかもマイナス面として①放射線による発がんの増加②病気の見落としによる治療の遅れ③治療不要な病気の発見による不要な検査・治療の副作用④膨大な費用などが指摘された。これで、健康診断を薦める通達はなくなるかと思ったがどういうわけか握りつぶされてしまった。そしていまだに厚労省の通達のために職場検診が行われて意味のない受診させらている人たちがいる。本当に気の毒なことである。
「ジャイロモノレール」
令和元年8月16日
今日から診療開始である。例年、休み明けは患者さんが多く、休みから仕事モードに移るのが結構しんどいのだけれど、今年はそれほどでもない。昨日は大型台風が広島県を縦断したが、本当に台風が来たのかと思うほど風雨は少なく、新幹線をはじめ在来線・バスなどすべて予定運休になったがその必要があったのかと思ってしまう。デパートも臨時休業になるし、甲子園も中止になった。羹(あつもの)に懲りて膾(なます)を吹くということわざがぴったりではないか。
表題は工学博士で作家の森博嗣氏の著書である。氏の趣味の模型作りの一環として始めた「ジャイロモノレール」の試作と成果を発表したものである。この装置は100年以上前に開発・実用化されたが、その技術は長く忘れ去られ再現不可能とされていた。氏は理論的には可能と考え、実験と試作をくりかえしついに完成させた。理論については氏の丁寧な解説にも関わらず自分には難しくて理解できない部分もあるが、現に完成され一本のレールの上を安定して走らせているのだから素晴らしい。
あとがきで氏は「趣味」という言葉について、欧米でのhobbyの概念と日本のそれの違いについて語っているが、日本ではレジャーやスポーツは趣味に含まれるが欧米ではそうではないという。hobbyとは紳士の嗜みとして仕事より重視されるもので、品位を形成するものとされているそうである。定年になってあわてて「趣味」を探すようなものではないのだ。そうだとすれば自分にはhobbyはあるのだろうか。
「文豪たちの悪口本」
令和元年8月9日
表題は文豪と呼ばれる作家たちが他の作家、友人、家族、世間に対して愚痴やあてつけ、悪口など書いていて、その現存している文章や手紙、日記、友人や家族の証言を集めたものを彩図社文芸部が編集したもので、作家たちの人間的な一面が垣間見えるのが面白い。
太宰治は芥川賞がもらいたくて選考委員だった川端康成に働きかけたがかなわず、怨念の手紙を川端に書き送っている。青森の大地主の坊ちゃんの太宰治だけれど、よほど賞金が欲しかったとみえる。夏目漱石の妻鏡子に対する愚痴も面白く、妻鏡子からみた漱石についてのくだりも、漱石がかなり気難しい人だったことが伺えて笑える。文芸春秋を発刊した菊池寛への永井荷風の嫌悪は死ぬまで続いて、荷風の「断腸亭日常」には折に触れて菊池寛への非難の文章が残っている。谷崎潤一郎と佐藤春夫の書簡のやり取りも残っているが、谷崎の妻千代に恋愛感情を持った佐藤が、千代に飽きていた谷崎から千代を離縁してもらい受ける約束をしていたのに、一旦反故にされたことを恨んだ手紙のやり取りが面白い。結局、千代は佐藤春夫の妻になるのだが。
当時の作家の地位は高く、文豪と呼ばれるほどの作家はオピニオンリーダーであり、尊敬の対象であり、スターであったが、こういう文章や手紙などをみると我々と同じ凡人の面も見られて面白い。
宇品の花火大会
令和元年8月2日
7月最後の土曜日に例年通り宇品港1万トンバース沖で花火大会が行われた。いつもは用事があったり面倒だったりで行かなかったのだが、今年はちょうど夕食も済んでほろ酔い気分でもあり、久しぶりに行ってみた。宇品港までは自宅から真南に2キロちょっとの距離であるが、周辺は人が多すぎるので海岸通りから見ることにした。1万発の花火が準備されていてこれを1時間であげるわけだが、夏の夜空を彩る音と光は百花繚乱の装いを呈していてこれほど素晴らしいものはあるまい。大きく広がる光と腹に響く音、火薬のにおい煙など五感を刺激して昔の夏の記憶をよみがえらせてくれる。学生時代から聞いていた男声合唱組曲「雪と花火」のなかの「花火」という曲がずっと頭の中を流れていた。北原白秋の東京景物詩のなかの「花火」に多田武彦が曲を付けたものである。
花火があがる 銀と緑の孔雀玉… パッとしだれてちりかかる
紺青の夜の薄あかり ほんにゆかしい歌麿の 舟のけしきにちりかかる
花火が消ゆる 薄紫の孔雀玉…紅くとろけてちりかかる
Tron…Tonton…Tron…Tonton 色とにほひがちりかかる
両国橋の水と空とにちりかかる
花火があがる 薄い光と汐風に 義理と情けの孔雀玉…涙しとしとちりかかる
涙しとしと爪弾きの 歌のこころにちりかかる
団扇片手のうしろつき つんとすませどあのように 舟のへさきにちりかかる
花火があがる 銀と緑の孔雀玉…パッとかなしくちりかかる
紺青の夜に大河に 夏の帽子にちりかかる
アイスクリームひえびえと ふくむ手つきにちりかかる
わかいこころの孔雀玉 ええなんとせう 消えかかる