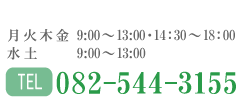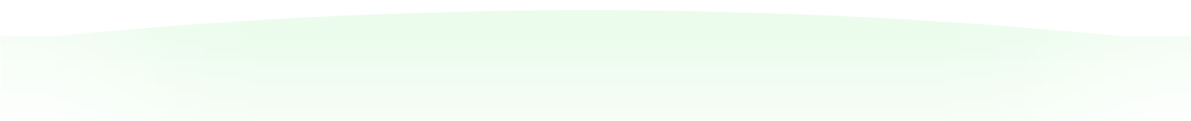平成26年8月9日(土)
表題は関東医療クリニック院長、松本光正氏の著書名である。氏は長年、高血圧症や高脂血症などの成人病(今は「生活習慣病」といって、本当の原因である「老化」を隠してあたかもきちんと生活しなかった本人のせいだといわんばかりの呼び方である)を診てきたが、これまでの経験とさまざまな新たにわかってきたデータから、上記の結論に達してそのように診療しているという。
ヒトの体は自然にそれぞれ最も良い状態になる力があり(これをホメオスタシスという)血圧が高くなるのはそれなりに理由があるわけで、無理に下げると脳梗塞になりやすくなる。氏は高血圧症の基準値をWHOが8年間で50も下げたことに憤りを感じている。WHOは予算の7割を製薬会社の寄付金に依存している。降圧剤は製薬会社にとってドル箱である。高血圧症の基準値を下げれば患者が増えるのはあたりまえである。それらも含め氏は「血圧計は捨てなさい」など一見過激に思えることを提唱している。そういえばかの有名な近藤誠医師も「私は何十年も血圧を測ったことがない」と書かれていた。
実は私もここ1年血圧を測っていない。
カテゴリー 本
高血圧はほっとくのが一番
藤原正彦著「ヒコベエ」
平成26年7月4日(金)
表題の「ヒコベエ」は「若き数学者のアメリカ」「遥かなるケンブリッジ」など興味深い著作を持つ数学者、藤原正彦氏の自伝小説である。氏はベストセラー「国家の品格」をはじめ、エッセイなど精力的に著しているがこの「ヒコベエ」は、著者の記憶の始まる3~4歳ごろから小学校を卒業するまでの自分史・家族史を中心に、戦後の混乱・復興期の世情が描かれていて読み出したらやめられなくなるほど面白い。
「ヒコベエ」は著者の幼小期の呼び名で、元気一杯・猪突猛進・ガキ大将、それでいてやさしくてユーモアのある氏にぴったりである。氏の母親は終戦後満州から幼い3人の子供を連れて命がけで引き上げた体験を書いた「流れる星は生きている」の著者、藤原ていであり、父親は気象学者で直木賞「強力伝」で知られる作家、新田次郎である。さすがカエルの子はカエルで、氏は数学者としての業績の上に興味深い本を多数著して多くの読者の支持を得ている。今は週刊新潮に毎週エッセイを載せているが、面白く読ませてもらっている。
次は、「ヒコベエ」と「若き数学者のアメリカ」のあいだ、思春期から青年期の自伝小説を読んでみたいものである。
沢木耕太郎著「無名」
平成26年1月10日(金)
著者は20代の頃からノンフィクションの分野で佳作をいくつも著し、当時から注目し愛読していたライターである。「若き実力者たち」「敗れざる者たち」「人の砂漠」「テロルの決算」など夢中で読んだものである。最も面白かったのは「深夜特急」で、著者が書くという仕事を始めて4年目にユーラシアからパリへの長い旅に出た時の体験を書いたものだった。特に旅を始めたばかりの香港、マカオ、インドなどでの体験は、当時の自分も若かったのでまるで自分がそこにいるかのように感じられ興味深く読んだ。
その後、著者のエッセイなどを時々読んでいたが、デビューの頃の鮮烈さは薄れていた。そうしているうちに壇一雄未亡人の一人称話法に徹した作品「壇」を発表し、改めて注目するようになった。そして2003年にこの作品「無名」が刊行された。これは無名の、一市井の人として亡くなった著者の父親の人生の軌跡を、病床の父を見守りながら、幼少時からの記憶を掘り起こして書き綴ったものである。著者の父親に対する心情と父親の息子に対する気持ちが伝わってきて、心が洗われる思いがする。まことに稀有な作品である。
世界はだいたい日本の味方
平成25年12月20日(金)
表題は新潮45、1月号の特集である。日本に住んでいる外国人から見た日本という国と日本人について、14人のさまざまな国の人たちが書いている。さらに3人の中国人の若者が匿名で日本について話し合う。日本に対して好意的な人を選んでいるのだろうが、実際彼、彼女たちが言っていることは的を射ている。曰く「すべてがそろっている奇跡の国」「この国にいると心穏やかになれる」「日本はいい国である」「世界に誇る伝統文化とお出し汁の味」「スイスにはない楽しさと自由」「ありがとうとお互い様の心」「やさしい人々が住む安全な国」「緑豊かな自然、四季を感じる暮らし」など。
ロシア、欧米の国々が開国をせまり、それまで鎖国を貫いていた徳川幕府も外国と付き合わざるを得なくなった。レベルの高いこれらの国々に対処するために、明治以降日本人は一生懸命頑張ってきたと思う。それまでの日本の制度をいったん白紙に戻し、議会制民主主義を取り入れ憲法、民法などすべてを欧米にまねて作り上げ、さらに工業化も進めた。その後色々なことはあったが、世界の多くの人たちがうらやむような現在の国を作り上げてきたのである。
「世界はだいたい日本の味方」というのは、隣国の日本に対する敵意と仕打ちを苦々しく思っている多くの日本人への激励の言葉だろう。心強いことである。
どんな病気でも後悔しない死に方
平成25年11月8日(金)
表題は緩和医療医、大津秀一氏の著書である。氏は千人を超える人たちの緩和医療に携わってきた経験から、終末の医療について述べている。人は必ず死ぬので、最期を迎える時にどうしたら後悔しなくてすむのか、病気ごとにわかりやすく説いている。一貫した主張は「ほとんどの病気には治療が効かない段階が来る、そこからの苦しいだけの延命治療は控えて、自分のため家族のための最後の時間は大切にすべき」と説く。
氏はやすらかな最期が迎えられるように本人、家族と真剣に話し合い方法を探る。一人ひとり状態が異なるわけだから、それぞれの解決策は異なるわけである。じつに考えさせられる内容である。確かに自分たちもいずれ必ず死ぬのだから、日頃からどのようにするか考えておくことは必須である。そのための参考書としてすぐれた本だと思う。尤も氏の本音だと思われるが、「自分の理想とする死に方は、平均年齢まで生きて普段から皆に、ありがとうな、おじいちゃんはそのうち死ぬから後は頼むな、と言い含めある夜心疾患で寝ている間に苦しまず亡くなる」というものだが、これは宝くじに当たるぐらい難しいだろう。
近藤理論への反響
平成25年10月25日(金)
近藤誠医師の「医者に殺されない47の心得」は100万部のベストセラーになり、同時期に出版された「余命3カ月のウソ」「抗がん剤だけはやめなさい」「がん放置療法のすすめ」なども合わせると今、最も影響力のある本である。近藤氏が1996年に著した「患者よ、がんと闘うな」以来、一貫して世界中の論文、データ、自身の診療からの経験を通して訴えていることは、患者さんを治そうとすることがかえって苦しめることになっている事実に警鐘を鳴らしていることである。医学界からは反論はあったが、近藤氏の緻密な理論を論破できず「無視」をきめこんでいた。
最近、新潮45、11月号に掲載された西智弘医師の「近藤誠はなぜ売れるのか」という文章を読んだ。西氏は近藤理論をほぼ否定しており、「抗がん剤は効く」と主張しておられる。問題なのはその根拠が、自分の経験では○○さんには効いたという実例をあげての理論で、近藤氏のデータと論文をきちんと分析したうえでのそれと比べると説得力がないことである。
新潟大学名誉教授岡田正彦氏の「医者とクスリの選び方」を読むと、近藤氏とほぼ同じことを述べていることがわかる。曰く、「がん検診は有効でない」「抗がん剤は効かない」「健康診断、ドックは長生きに無関係」「薬をたくさん出す医者は要注意」など、近藤氏の主張を代弁しているかのようである。真実というものは変わらないものだと思った次第である。
山崎豊子氏の作品
平成25年10月4日(金)
話題作を量産した作家、山崎豊子氏が亡くなった。氏の作品を初めて読んだのは高校時代、「白い巨塔」「続・白い巨塔」で、大阪大学をモデルにしたことがすぐにわかる「浪速大学」が舞台になっていて面白かったのだが、医学部を目指していた自分としては大学病院というのは怖いところだと思ったことである。話のポイントは財前教授が癌を見逃したために患者が亡くなるというところであるが、この点には疑問符がつくが細かい点がきちんと描かれていて今読んでも新鮮である。その後盗作問題などが話題となって、この作家に対して興味を失っていた。
十数年前、ふと本屋で見つけた吉本興業の創業者「吉本せい」をモデルにした「花のれん」を読んで面白さにはまって、文庫本になっている作品はほぼすべて読んだ。大阪商人でも特権階級といわれた「船場」で生まれた作者は、さすがにこの分野は詳しく思い入れもあり実に興味深く読ませてもらった。最も面白かったのは足袋問屋の後継ぎ息子の、家つき娘だった母、祖母たちとの葛藤を芯に、その成長と放蕩を描いた「ぼんち」で、この人でなければ書けない作品だろう。それにしても力のある作家だったと思う。合掌。
井川 樹著「ひろしま本通物語」
平成25年8月22日(木)
本通りの近くに開業して16年、いつも身近に感じていた「本通り」の本が出版された。著者は広島に住んで30年、広島一、中四国一の商店街でもある「本通り」を愛する一市民、消費者として著したという。
「本通り」は旧山陽道「西國海道」にほぼ重なっており、現存する最も古い赤松薬局は、広島城が築かれた1615年に現在の場所に店を構えている。浅野家の広島入府に従って、和歌山から大勢の商人が追随した。とらや、みたや、てんぐ、永井紙店、おくもと、などがそうである。当時から商業地として栄えており、明治、大正、昭和と次第に現在のような商店街になってきた。原爆による壊滅にもかかわらず、関係者をはじめ多くの人の努力により復活し、週末ともなると1日10万人が繰り出す繁華街になっている。クリニックの近くにある「アンデルセン」は本通りのランドマークとして、買い物、食事、会合などに重宝している。
他にも「本通ヒルズ誕生の秘密」「ひろしま夢プラザはなぜ成功したか」「裏袋から見た本通り」などの章があるが、興味深いのは本通りの商店を克明に記した地図が、「被爆前」「昭和32年頃」「平成12年」「現在」と時代別に掲載されており、商店そのものの変遷が一望できることである。開業したばかりの頃足繁く立ち寄っていた「丸善」もずいぶん前になくなった(最近、天満屋の跡に復活しているが)。この店は3階まである本屋だったが、2階には紳士用品の店と本通りを眺めながらうまいコーヒーの飲める喫茶室あり、よく利用したものだった。こんなことを思い出すことができたのも、この本のおかげである。
南木佳士の著書
平成25年7月19日(金)
医師であり芥川賞作家、南木佳士の著作は、受賞作「ダイヤモンドダスト」以来、ほとんど読んでいる。群馬県の寒村で生まれ、3歳の時に母親を結核で亡くし祖母に育てられた。中学2年の時に東京郊外の再婚した父親のアパートで孤独な日々を送りながら医師を目指して受験したが、不合格。1浪して秋田大学の医学部に進学、卒業後は郷里に近い長野県の佐久総合病院に勤める傍ら著作を始める。独特の視点ときめの細かい文章で、一定のファンを獲得している。年齢は私より1歳上で、共感を覚える部分が多く、特に精神的に落ち込んでいる時に読むと慰められるやさしさがある。
これらの著作を読んでいていつも思うのだが、優れた作家は書きたいものがあり書かずにいられないのである。それにしても著作だけで生活していく作家は、職業として成立させるのは難しいだろう。特に活字離れの進んだ現代では稀有な存在になっているのではなかろうか。
鮮やかに生きた昭和の100人
平成25年7月11日(木)
表題の本は文芸春秋90周年記念に5月臨時増刊号として発刊された。昭和の時代に活躍し、現在は亡くなられた100人の写真と紹介文を1冊にまとめたものである。昭和天皇をはじめ、作家、政治家、芸能人、スポーツ選手、財界人などいずれも昭和を代表する人たちである。写真を見ながら文章を読んでいると、その当時の生活の日々が思い出されて感慨深いものがあった。
もちろん、この人たち以外に優れた人は大勢いただろうし、無名でもすばらしい生き方をした人はもっとたくさんいただろう。それらの人たちの中でたまたまスポットライトがあたった100人というわけである。写真を見て共通していると思ったのは、どの人も姿かたちが良く加えてたたずまいに魅力があるということである。やはりどの分野であれ「魅力がある」ことが一番だと思ったことである。