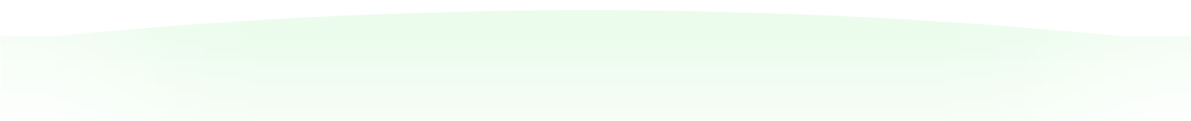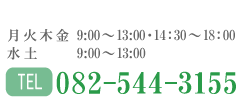平成24年12月5日(水)
表題は以前紹介した中村仁一医師と近藤誠医師の対談である。二人とも医師として全く違った道を歩んできたけれどもほぼ同じ考えになっていることがわかる。いわく、「死ぬのはがんにかぎる、ただし治療しないで」「がんの9割に抗がん剤は無効」「老化は治療できないのだから医療機関に近づくな」「ワクチンやってもインフルエンザにかかる」「高血圧の基準値の変更で薬の売り上げが6倍になった」「検診はムダだ」など、様々な点で意見が一致している。
思うにお二人とも経験と理論から「がん」「老化による変化」は治せないと確信し、患者に苦しみしか与えない治療を受けないように警鐘を鳴らしているのだろう。そして「こういうことを言えば医療界では村八分になる」とわかっていても言わずにいられない情熱と勇気がある。
1800年代のヨーロッパにセンメルヴェイスというハンガリー人の産科医がいた。彼はウイーン総合病院の産科に勤務していたが、自宅分娩や助産婦が行う分娩と医師が行う分娩では産褥熱の発生率が10倍も違う(助産婦では死亡率3%に対して医師では30%!の死亡率)ことに疑問を持ち調べた結果、医師が手指消毒すればよいことに気づきそのようにしたところ産褥熱は激減した。これを当時の医学会で発表し医師たちに消毒の大切さを説いたが、学会では受け入れられなかった。ウイーン総合病院の任期が切れ除籍した後、妊産婦の死亡率が3%から30%に増えたのを見たセンメルヴェイスは、各病院をまわり消毒の大切さを説いたが相手にされず悲惨な最期を遂げた。のちに彼の説の正しさが追証され「院内感染予防の父」と呼ばれるようになった。
近藤医師、中村医師とセンメルヴェイスは同じように思える。