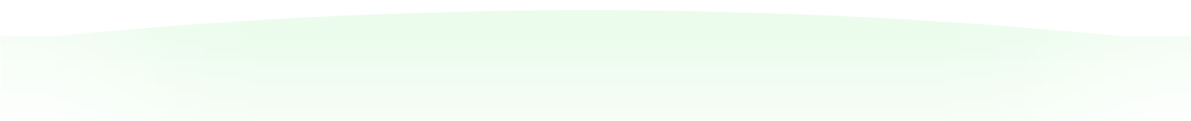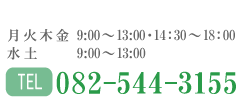平成24年7月27日(金)
表題は元国立公衆衛生院疫学部感症室長の母里啓子氏の著書の題名である。氏は医学部卒業後ウイルス学を修め、感染症の対策に一貫して携わってきた人である。現在B型肝炎の垂直感染を防ぐことができるようになったのは、母里氏たちの功績によるところが大きい。いわばワクチンのプロである。
氏によると、インフルエンザウイルスは変異が激しく流行に合わせたワクチンをつくることが難しいそうである。そもそも不活化ワクチンの外部に通ずる粘膜感染予防の効果は疑問視されているが、インフルエンザワクチンは不活化ワクチンである。一方、インフルエンザは高熱が出るとはいえただの「風邪」である。暖かくして安静にしておけば治る。一度かかると強力な抗体ができ、少々違う型のウイルスにも効果があり、流行があってもブースター効果でかえって抗体価が高くなる。インフルエンザのワクチンを打つ意味はない。まして副作用があるのである。母里氏は専門家として正しいことを発言しないのはよくないとの信念のもとに、逆風覚悟で発言しておられる。
日ごろからインフルエンザワクチンについて思っていたことと一致して、わが意を得たりという気持である。さらに氏は子宮頸がんワクチンについても、このワクチンは不活化ワクチンであり粘膜感染予防効果には疑問が残るとしている。もともとHPVは感染してもほとんどは消えてしまうウイルスであり、たとえ感染が持続して異形成となってもなんら害はなく、その後がん化しても早期発見すれば治療できるものなので、わざわざ高価なワクチンを打つ意味があるのかと述べられている。まさに的を射た提言で、医療者は傾聴すべきである。