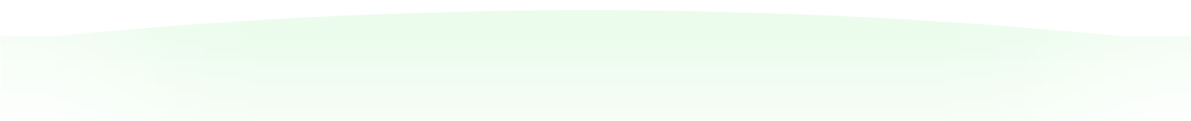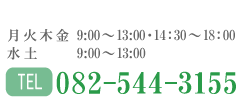平成24年2月23日(木)
著者の中村医師の父親は、医者になりたくて苦学していた20歳の時に、受診した眼科で目薬と消毒薬を間違えて点眼され失明したためあんまの技術を身につけてやっと一家を養っていたが、著者が高校生の時に心筋梗塞で亡くなった。それもあって著者は医者になろうと思い京都大学医学部に合格したが学費も生活費もなく、すべてアルバイトで頑張って卒業し医師になった。その後病院の院長を経て現在、特別養護老人ホームの医師をしている。市民グループ「自分の死を考える集い」を主宰して16年になるという。
著書の中で、「生、老、病、死」は避けられないことだから、さからわず受け入れていくことがすべてだという。生き物は繁殖し、繁殖を終えたら死ぬのはあたりまえで、それにさからうことは不可能である。ホームで何百人もの自然死を見ていると、病院で医療を受けつつ死ぬよりはるかにやすらかに逝けることがわかる。医療にかかわらない方がいいのである。死は怖くないことがわかれば死を正面から見つめることができ、だからこそ「今」を精一杯生きようとすることができる、とユーモアを込めて説く。
医療の限界を知ってしまった著者は、生きることと医療のかかわりをまことに的確に述べている。さらにこの書は「老化」を治療の対象にしている現代医療へのアンチテーゼでもある。感染症やけがなどは原因を取り除けば治癒するが、「老化」による変化は治療できるわけがない。それを「生活習慣病」と称して賽の河原の石を積むようなことをしている現代医療と、それを信じて従っている人々に警鐘を鳴らしているのである。なかなかユニークな正鵠を射た考え方であると思う。